アレルギーとは?
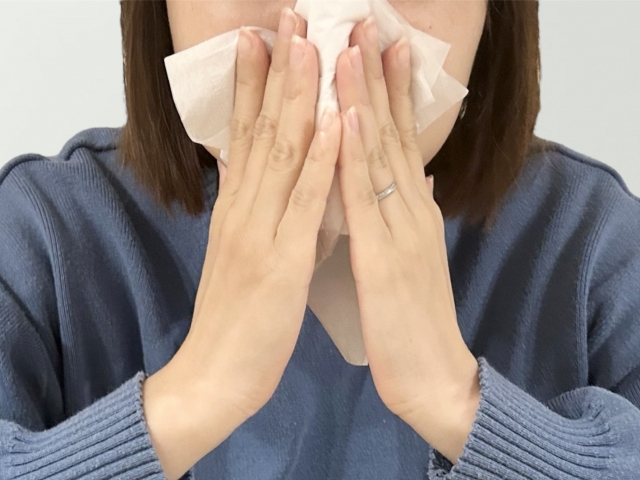
本来、体に無害な物質(アレルゲン)に対して、体の免疫システムが過剰に反応してしまう状態をアレルギー反応と言います。原因となる物質や体質によって様々な症状が引き起こされ、症状の程度によってはQOL(生活の質)を損ねる要因となります。
大船・横浜市栄区の小笹医院では、花粉症をはじめとする様々なアレルギー疾患の検査・治療を行っています。詳細な問診と適切な検査により、アレルギーの原因を特定して、個々の症状や生活環境に合わせた治療計画をご提案いたします。
アレルギー症状でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
代表的なアレルゲン
アレルギー反応を引き起こす代表的なアレルゲンには、以下のようなものがあります。複数のアレルゲンに反応する場合もありますので、年間を通じてアレルギー症状がある方は、検査による原因特定をおすすめします。
- 植物花粉(スギ、ヒノキ、イネなど)
- ハウスダスト
- ダニ
- ペットの毛
- 皮膚のフケ
- カビ
- 特定の食物(卵、乳製品、小麦、甲殻類など)
- 特定の薬物
- 昆虫(ハチなど)の毒 など
花粉症について
花粉症は代表的なアレルギー疾患の1つで、スギやヒノキなどの植物の花粉によって引き起こされます。
主な症状は、鼻の症状(くしゃみ、さらさらとした鼻水が出る、鼻づまり)、目の症状(かゆみ、充血、涙目)、そして全身症状(倦怠感、集中力低下)などです。体質によって症状の程度には差がありますが、重度の場合、日常生活や仕事、学業に支障を来すこともあります。
スギやヒノキ花粉が飛散する3月から5月にかけて、症状を訴える方が特に多いです。しかし、反応する植物花粉によっては夏以降に症状が現れる可能性もあり、複数のアレルギーを持っていると年間を通じて花粉症が続くこともあります。
| 代表的な植物 | 飛散時期 |
|---|---|
| スギ | 2~5月 |
| ヒノキ科 | 3~5月 |
| シラカンバ(カバノキ科) | 4~6月 |
| イネ科 | 6~9月 |
| ブタクサ科(カバノキ科) | 8~10月 |
アレルギーの検査と診断
アレルギー診断の第一歩は詳細な問診です。症状の特徴、発症時期、環境要因などを確認してアレルギーの可能性を評価します。続いて各種検査を実施して、アレルゲンを特定したうえで最適な治療計画を立てていきます。
血液検査(View39)
特殊な血液検査により、39種類の主要なアレルゲンに対する体内の抗体量を一度に測定できます。少量の採血で花粉、ハウスダスト、食物など多岐にわたるアレルゲンを特定可能なため、効率的かつ包括的なアレルギー検査として有用です。
検査結果をもとに、アレルゲンの回避や適切な治療方法を提案いたします。
アレルギーの治療
アレルギー治療の基本は、アレルゲンの回避です。しかし花粉やハウスダストを完全に回避するのは難しいため、症状に合わせた薬物療法を行い、不快な症状を抑制します。
薬物療法
内服薬(抗ヒスタミン薬など)
くしゃみや鼻水、かゆみなどのアレルギー反応を起こす物質の作用を抑える薬です。適切なものを選択、あるいは併用することで症状を緩和します。
点鼻薬・点眼薬
鼻や目に直接作用して、症状を改善します。全身への影響が最小限で即効性が高いため、つらい局所症状の緩和に効果的です。
舌下免疫療法
アレルギー症状の根本的な改善を目指す治療方法です。原因となるアレルゲン(スギ・ダニなど)のエキスを少量から始めて徐々に増量し、毎日舌の下に置いて体を慣らしていきます。長期的に継続することで、免疫システムがアレルゲンに対して寛容になり、症状の軽減や薬の減量が期待できます。
効果が現れるまでに数か月から数年かかりますが、アレルギーの根本原因に働きかける治療として注目されています。
日常生活での予防とセルフケア
アレルギー症状の緩和や予防には、薬物療法と併せて適切な生活習慣の改善が重要です。アレルゲンとの接触を可能な限り減らし、体調管理を行うことで症状を軽減することが可能になります。
アレルギーの種類別に効果的な対策をご紹介しますので、ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。
花粉症
- 花粉の飛散情報をこまめに確認する
- 飛散量が多い日は外出を控えるか、マスクやメガネを着用する
- 帰宅時は衣服や髪についた花粉を払い落とす
- 顔や手を洗い、うがいをして花粉を洗い流す
- 洗濯物は室内に干すか、乾燥機を利用する
- 窓を閉めて、空気清浄機を活用する
など
ハウスダストやダニのアレルギー
- こまめな掃除や換気を行う
- 寝具のこまめな洗濯・乾燥を心がける
- 布団乾燥機やダニ対策シーツを活用する
- 湿度を適度に保ち、ダニの繁殖を抑える
- カーペットやぬいぐるみなどのホコリが溜まりやすいものを減らす
など
食物アレルギー
- 原因となる食品を避ける
- 外食時は事前に成分を確認する
- 調理器具の共用に注意する
- アレルギー対応食品を活用する
- 緊急時の対応方法をご家族やまわりの方と共有しておく
など

